愛着デザイン
今日は昨日やぼろじ(昨日のブログ参照)で買った卵を目玉焼きにした。
生産の話も聞いたりして、ストーリーがあったので、スーパーで買った卵とはちがう存在感。焼き方もちょっと丁寧になる。(見た目は普通なんですけどね)
いままでのえんがわ教室のキーワードは、いまのところ「愛着」なのかな。と、思う。
「愛着」をつくるような、ストーリーや作り方、人の集い方などなど。
ただし、5年後やその先を考える。スーパーの卵に全部が全部ストーリーがあったら?
(もしかしたら、買う店のストーリーが細分化するのか。今で言う自然食品とか目利きスーパーとか)ちょっと面倒くさいなぁ。それにモノとかエリアとかのストーリーは自分でも作れる(小さい観葉植物が大きくなるまで育てたり。友達に誕生日にもらったり、ご近所付き合いを心がけたり)
ストーリーを必要とするもの、しないもの、必要としたほうがよいもの。
そこの線引きってどこなんでしょうね。
海外生活で好きになった、日本で見つからないような味のあるモノとかは
きっとその国を「もうしょうがないんだからー」とか、「すごくかっこいい!」とか「やっぱり優しいね」など愛着を持てるからなんだろう。他にも好きな要素はあるけれど。
逆にグローバルなものに愛着って、グーグルのロゴが遊んでいたりとか?
今日は会社でユニバーサルデザインの勉強をしばし。
定義は
○ユニバーサルデザインの7原則
1)Equitable use(誰でも公平に使える)
2)Flexibility in use(何通りかの使い方がある)
3)Simple and intuitive(説明書を読まなくても直感的に使える)
4)Perceptible information(必要な情報が早く簡単にわかる)
5)Tolerance for error(間違っても重大な失敗に直結しない)
6)Low physical effort(身体に負担をかけることなく使える)
7)Size and space for approach and use(使いやすい適度な大きさと広さ)
※ノースカロライナ州立大学デザイン学部・ユニバーサルデザインセンターの定義
5の失敗に直結しない、というのにひっかかりました。
たとえば駅のホームドア(なんて言うの?)とか、パソコンのエラー操作の時の音。
人って失敗することを前提に作られているもの。気になる。
これを「自治」という言葉にあてはめるのは少し面白いかも。と思いました。
ちくまから出ている物語の役割は人とストーリーのお話。ちょっと関係あったかな。

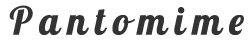


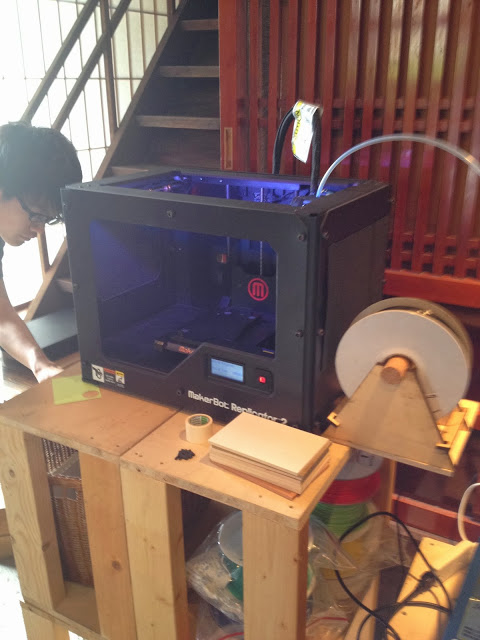


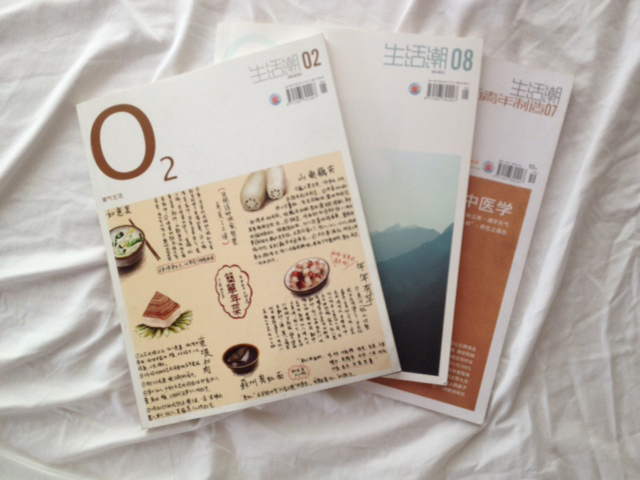




コメントを残す