「梅棹忠夫のことば」より
図書館で借りてきた「梅棹忠夫のことば」より。
お昼休みに読めてしまいますよ。
いくつか抜粋します。
「なんにもしらないことはよいことだ。自分の足であるき、自分の目でみて、その経験から、自由にかんがえを発展させることができるからだ。知識は、あるきながらえられる。あるきながら本をよみ、よみながらかんがえ、かんがえながらあるく。これは、いちばんよい勉強の方法だと、わたしはかんがえている。」
まず、一番はじめがこれ。
まず、このひらがなの多さに共感。
編集さんのコメント>「なんだ、そんなことも知らないのか?」と怒られて、一念発起する。そんな人生もありだけど、それよりは、「知らなくてもいいんだよ」とか「これから始めりゃいいさ」なんて言ってもらった方が勇気づけられるだろう。
梅棹さんは世界をぐるぐる足でまわった学者さん。いろんな国の人の生活を事細かに
メモしたのです。(編集術の達人でもあった)生まれは1920年の京都の方です。
ちなみに今年は2013年です。たぶん。
「現地で、実物をみながら本をよむ。わたしはまえから、これはひじょうにいい勉強法だとおもっている。本にかいてあることは、よくあたまにはいるし、同時に自分の経験する事物の意味を、本でたしかめることができる」
ほう。知識の取得と同時にモノがあればたしかに経験として学べる。美術館ガイドとかは、典型だけど、ワークショップとかも近いのかな。知識いれてもらいつつ、何かするとか。
「なにごとも、かきとめておかなければ、すべては忘却のかなたにおきさられて、きえてしまう。歴史はだれか他人がつくるものではなくて、わたしたち自身がつくるものだ。わたしたち自身が、いまやっていることが、すなわち歴史である」
一年後の自分は他人、だから誰にでもわかるようにメモしないとね。というお話もあり。きっと何年もかきつけたメモを、時間を越えて編集して発見したことがたくさんあったからこその言葉なのかなと。ひとつのプロジェクトが始まる時も、チームの中でのキーワードなどをカテゴリ別にメモって、あとで俯瞰したりすると楽しいかもーと思いました。
「人類史のながいながれのなかで、一番はじめにでてくるいとなみは「腹の足し」になることです。そこで農業をやり家畜を飼う。二番目にでてくるのが「体の足し」になること、つまり、体がらくになる。あるいてゆくところを電車でゆくとか自動車でゆくとか、エネルギーの足しになることをやる。これがつまり工業化ということです。三番目にでてくるのが「心の足し」。これが文化という概念でとらえようとしているものでしょう」
今の日本は農業(腹の足し?)のこととか、東洋医学(体の足し?)、そしてそれを絡めた「心の足し」がいろいろあるような。あれ、なんかちがうかな。
「最後にもういちど、思想はつかうべきものである。」
とのこと。
よい週末を。

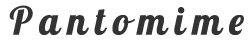
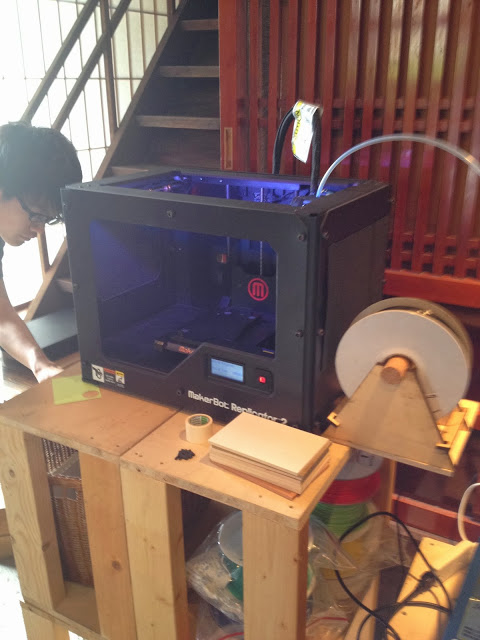
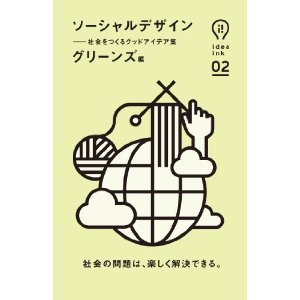
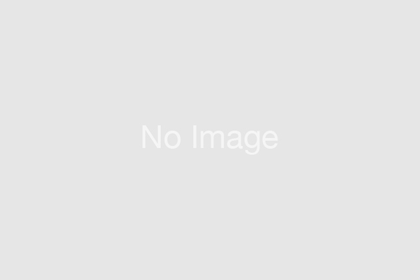





コメントを残す