2013-04-28
福島で震災時のお話をうかがいました vol.2
こんにちは、前回のつづきを書きます。
JR常磐線の跡もみました。いまでは普通の道しかありませんでした。
当時JRの規則で、「運転手は絶対に車両を離れてはならない」とあり、
運転手さんは乗客が逃げた後も、ぎりぎりまで車両を離れなかったそうです。
最後は駅のホームにかかっていた橋に逃げ、助かったそうです。
その後、JRの規則は乗客が逃げたら、運転手も逃げて良いことになったそうです。
 |
| 道路脇にたてられていた碑 |
地震のあとご夫婦は市役所の避難所に逃げたそうです。
その避難所では、備蓄のカンパンがくばられました。
その避難所では、備蓄のカンパンがくばられました。
カンパンには中に氷砂糖が入っているそうです。あの堅い食べ物をお年の方や
赤ちゃんがたべるにはとても厳しいものがあります。
カンパンも足りないなか、思い出されたのはお客様用にコンビニで買い占めた
おむすび。(vol.1参照)
ご自身が次にいつ食べることができるのかも分からない中、
「中身のことは好き嫌いいわずに、とにかく受け取って食べてください!」
おむすび。(vol.1参照)
ご自身が次にいつ食べることができるのかも分からない中、
「中身のことは好き嫌いいわずに、とにかく受け取って食べてください!」
と、避難所にいた方全員に配ったそうです。配ったおむすびは、避難所のいた方と
数がぴったり同じだったそうです。ご先祖なのか、神様なのかわからないけれど、
数がぴったり同じだったそうです。ご先祖なのか、神様なのかわからないけれど、
何かに守られている感じがしたそうです。
避難所では当時、箸も皿もなかったので割り箸やカップ麺の器を洗って、
再利用していたそうです。しかし、何度も使ったお箸には醤油染みなどがつき
湿っていたそう。辛かったそうです。
湿っていたそう。辛かったそうです。
また、避難所にとどいたインスタントヌードルが、辛いエスニックの物しか
なかったそうです。正直おどろきました。
なかったそうです。正直おどろきました。
私は、被災された方は日本食の差し入ればかりで、きっと(私のような)エスニック好きな方は
元気がなくなると思い、エスニックフードを送ったりしたのですが、現実は違いました。
避難所では、みなさんとても優しかったと旦那さんは言いました。
しかし、一ヶ月たつにつれ、半年がたつにつれ、色々な物や環境が整うにつれ、
仮設にも、震災後沢山のおもちゃが届いたそうです。
よかれと思って送ったおもちゃも、子どもたちに日々届き与えられ続け、
いつしか物の大切さを子どもたちは見失っていきました。
いつしか物の大切さを子どもたちは見失っていきました。
それではいけないと、大人たちは支援されたおもちゃなどを使い、
子どもたち自らがお店をする一日マーケットを開く企画をされたそうです。
子どもたち自らがお店をする一日マーケットを開く企画をされたそうです。
おもちゃのビーズセットを使って、作った腕輪を売ったり、
作って売ることで、物への大切さの気持ちを育んだそうです。
救援物資を送るにしても、どのような物が必要とされているかを
お話いただいた奥さんは、仮設で孤独死や自殺者など出したくない。
だから、できるだけコミュニケーションをとっていきたい。
そういう思いで、「エコタワシを作って、温泉に行こう!」
と企画されたり、仮設を必要としなくなった方や近くの別の仮設の方にも
分け隔てなく参加を促されたりしています。
仮設のような非常時の人のコミュニティーでどのようなコミュニケーションを
とったら良いのか、というリーダー作りやこういう時だからこそのマニュアル
(お祭りやイベントなどいかに自然に皆をまきこむのか)があると良いなと思いました。
(お祭りやイベントなどいかに自然に皆をまきこむのか)があると良いなと思いました。
自発的にリーダーになる方がいない仮設もあると、思うのです。
 |
| 仮設のコミュニティースペース。お茶うけにお漬け物をいただきました。 |
新地では仮設の次、家に暮らす計画がすべての人に割り振られたそうですが、
まだいつまで続くのかわからない仮設生活をされている地域もあります。
また、東京電力からの補償金も過剰すぎるケースや、全くもらえないのに
大きな損害を受けているケースもあるようです。
県外への避難も、お金に余裕がないとできない場合もあったりと、
さまざまな問題が現在も続いています。
今回、見ず知らずの私に、勇気をもって震災のご経験を
お話していただいたことは本当に有り難いことでした。
せめてできることを、とブログに書きました。
お話していただいたことは本当に有り難いことでした。
せめてできることを、とブログに書きました。
今回お話をいただいたのは、朝日館という旅館をされていた村上さんです。
 |
| 中央が村上さん、ツアーを企画してくださった吉成さん(左) |
村上さんのブログはこちらです。今の福島は桜が咲いて、きれいでした。
http://asahikanok.exblog.jp/
http://asahikanok.exblog.jp/
タグ: 旅
関連記事

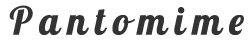

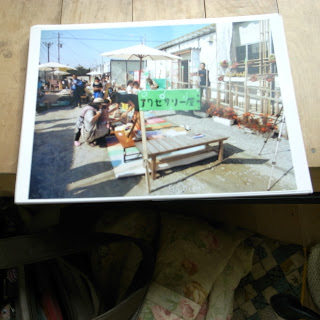


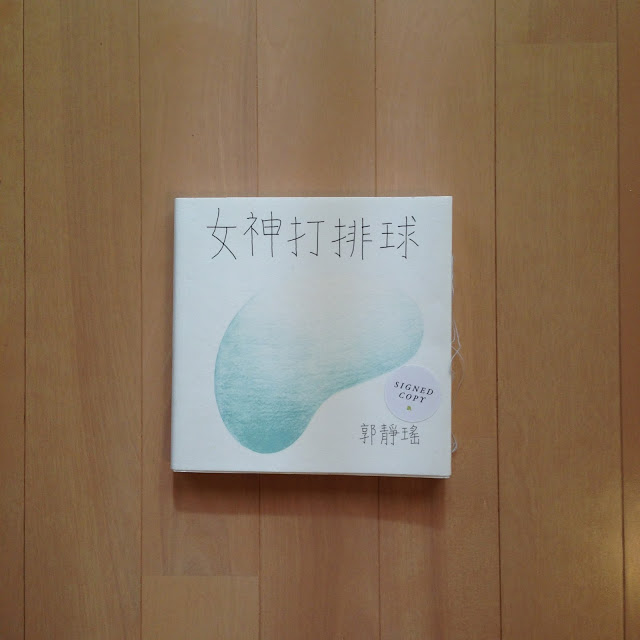






コメントを残す