ちいきのえんがわ教室 初日
もやもや。
会社づとめ、からはみ出ている未消化分のもやもやをどうにかしたく、「ソーシャルデザイン」を読んでみつけた、小平のタウンキッチン。(地域に根ざしたお惣菜屋さん)
そこではじまった「ちいきのえんがわ教室」に通う事にしました。
あまりソーシャルデザインとか、積極的ではないのだけれど、
こういう新しい世の動きに近い方たちの中で自分がどう変化するのか、試してみたく。
メンバーは30代〜で男性多めの7人。
企業をやめた方多め。シェアハウスに住んでる方、地域で何かしたいと模索中の方。などなど。
今日は自己紹介後、「ダイバーシティーdiversity」という単語について勉強。
多様性を認め合う、とかの意味で(他にも意味はあるのだけど)それについて話す。
個人で完結する時代に、どういう点でひととつながりを持ちたいのか、ダイバーシティーマネージメントという企業の人材戦略の話とか、地域という空間でこの考えはどう作用するのかな、などを話す。話す、話す、話す。
お昼は皆もちより一品のごはん。
はじめてのもちよりランチ。おいしゅうー!
つけものをもってくる人、牡蠣のオイル漬けの人、男飯な人、などなど。
もってきたものの、紹介なんかもして、その人がかいま見れたのも楽しく。
私はルクエで作ったポテト入り卵焼きをもっていきました。ちなみに、ルクエ。あの人工感がいやだなと、嫌っていたけれど、意外と便利で簡単で、おいしい。
午後は「いいファシリテーション facilitation」について話す。
・話しやすい雰囲気
・共通理解を形成していく
・脱線するときに戻す
・するどい質問ができる
・情報格差がなく、参加者の情報量が同じ
・中立/平等である
・着地点が見えている
など。ここから、議論はすすみ、コミュニケーションの構造化について。
混沌とした中から、いかにまとめていくのか、というのをステップを図解。
混沌→似た意見をまとめていく→そのグループの関係性をつくり→論点を設定
図がないと説明むずかしいのですね。スミマセン。
ふだん、仕事でやっていたことが実際に言葉となって、議論できるのは客観的で楽しい。
誰と話したことも、議論したこともないことだったから。
あと議論をホワイトボードなどにキーワードなどを書きつつ、まとめていくことも
意識的にしたほうがいいとわかりました。ホワイトボードを最近は使っていなかったんだけど、その良さを再認識。
それから、メンバーが今後やりたい「もやもやしたプロジェクト」を発表。
思っているアイデアをプレゼンし、本質を切り出すという高度なコミュニケーションでした。
例えば、話している本人が気づいていくような質問をする、「伝統」にこだわりのある人に「では(「伝統」とは真逆の)iphone」との違いは何?と聞いたり。(対極をしめすことは、言葉が明確になるステップになるそう)
プレゼン資料では、伝わらないことって多いな、と実感。伝わる資料ってなんだろう。
企画書を作ったりする仕事も、いままで多かったけど、いままでのやり方を再考する機会にもなりそう。
今回は「日本の伝統を生かしたものづくり」に興味のある方の発表と、「主婦と社会の接点をみつけたい」という方の発表でした。私は次回。
このもやもやが少しすっきりするといいなぁ。
しっかり「後押し」してくれる、よい機会にめぐりあったかんじです。
この「後押し」してほしいひと、いっぱいいるんだろうな。
「後押し」業ってのが、増えるのかな。
今後は、5月に国立のやぼろじで、イベントをする予定。
次回は西荻窪の、地域系の活動をしているところを皆でめぐる予定。
たのしい。
コメント2件
え、文章わかりやすかった?
うん。なんかね、おもしろいよ。
今度、W浅野の会でちょっと話すね〜

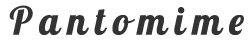



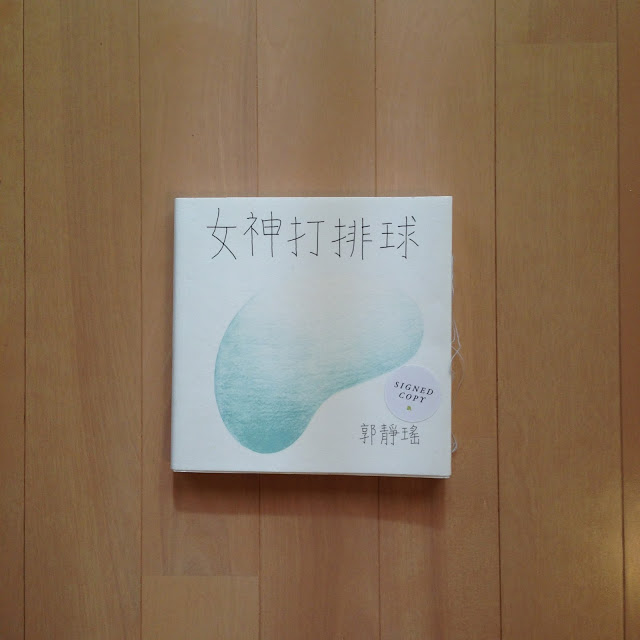






かこの文章わかりやすいね。
私には苦手な活動だけど、様子をのぞいてみたくなりました(^^)
ブログの更新楽しみにしてるね♪